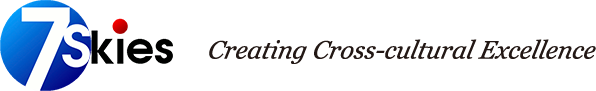78億人の希望を背負って2022年が明けました。当社も期待と不安が入り混じる新年のスタートを切りましたが、当社のお客様でもある運輸、観光、飲食等の業界にとっては、期待よりも不安が先行する展開となったようです。どれも日本の魅力的な文化や美しい風土を世界へ発信する、我が国の未来にとってなくてはならない産業です。追加の感染予防対策と、重症化防止対策の拡充を一刻も早く実行に移し、経済活動の正常化が加速するのを期待したいものです。
当社は、創業以来、プロジェクトマネジメントを通じてグローバル社会に貢献することを使命としてきました。仕事上、面識のない、言葉も、文化も異なるメンバーとプロジェクトを進めていく場面が多いのですが、同じ釜の飯を食わずとも、遠く離れていても、生活習慣が違っても、チームが同じ目標のもとに集まって共にゴールを目指せる背景には、情報通信インフラやソフトウエアの発達だけでなく、PMBOKに代表される共通のプロジェクトマネジメントのフレームワークの存在があります。お互いの違いを乗り越えて助け合う「叡智」が詰まったノウハウは、人類にとっての素晴らしい共有財産と言えるのではないでしょうか。
最近は国内のチームでさえ、実際に肩を並べ、膝を突き合わせて仕事をする機会がめっきり減りました。リモートワークは定着しつつありますが、中には離れて仕事をすること、相手が見えないことへの不安を抱えるケースや、非効率を懸念する声も少なくないようです。私自身はリモートワークのメリットを実感していますが、当社のように普段からコンサルタントがお客様の現場でサービスを提供している分散型組織にとっては、リモートワークによって節約できる通勤時間を、社内の勉強会などに充てられるようになり、社員同士の結びつきは(バーチャル環境で)むしろ強くなったように思います。
しかし、ハイコンテクスト文化と言われる日本の社会では、同じ釜の飯を食べていないと(同じ空気を吸ってないと)、本当に意思疎通出来るのか不安になるのも仕方ありません。誰かと自分の距離が離れるほど、相手は自分とは違っているかもしれないという不安が増幅されるのでしょう。ルトガー・ブレグマンは著書『Humankind 希望の歴史』で次のように書いています。「距離は人に、インターネット上の見知らぬ人への暴言を吐かせる。距離は兵士に、暴力に対する嫌悪感を回避させる。(中略)しかし、思いやりの道を選べば、自分と見知らぬ人との距離が、ごくわずかであることに気づくだろう。思いやりはあなたに境界を越えさせ、ついには、近しい人や親しい人と、世界の他の人々が、等しく重要に思えるようになる。」
リモートワークは、今まで目の前にいた相手、隣にいた同僚を、スクリーンの向こう側へ連れ去ってしまいます。ネット上では、同じ町でも、同じ国でも、地球の裏側にいても「向こう」であることに違いはありません。(なるほど、メタバースだと「こっち」の概念も生まれるのかもしれませんね!)こうして生まれる距離感がリモートワークにつきまとう不安や不信に繋がっているようにも思えます。その結果、ある種の分断が起きてしまっては、リモートワークは魅力的ではなくなってしまいます。逆説的ですが、もし私たちが、言葉の違いや見た目の違い、国籍の違いなどで、自分と距離を感じる相手に対しては思いやり(違いへのリスペクト)を示せているとすれば、今はその思いやりを、同じ言葉を使い、見た目も同じ仲間に対しても示すべきです。私たちは海外から訪れるゲストをもてなす文化を持っています。思っているほどお互いを「知らない」、一人ひとりは「違う」という現実を受け入れ、寛容の文化が根付けば、より多様性に富んだ社会が開けてくるのではないでしょうか。プロジェクトマネジメントの世界も、クライアントの要求事項を予め定義し、計画してから実行していくという「ウオーターフォール型」アプローチの限界を悟り、プロジェクトを進めながら要求元と受託側が相互理解を深めていく「アジャイル型」アプローチが主流となりつつあります。分断と対立ではなく、関心とリスペクトを肝に銘じて前へ進んでいきたいものです。
リモートワークがより豊かな社会へと繋がることを期待し、この一年、当社でも積極的に推進したいと思います。一方で、やはり生身の人とひとが会うことは、画面上の対面では味わうことのできない、息遣いと実感を伴います。人とひとの出会いは、お互いの人生を分かち合うことでもあり、生きている限りこれほど尊いことはないのではないでしょうか。仕事もプライベートも、一日も早く活発な人の往来が再開することを願いつつ、年頭の所感とさせて頂きます。
末筆ながら、皆様のご多幸と益々のご発展をお祈り申し上げます。
代表取締役社長 上甲哲也

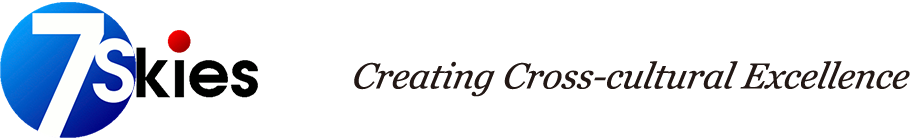
 English
English